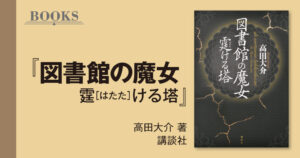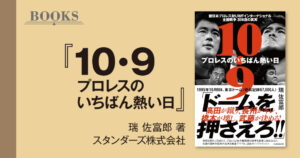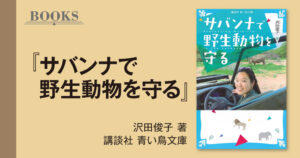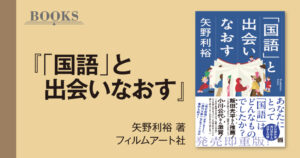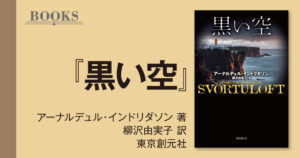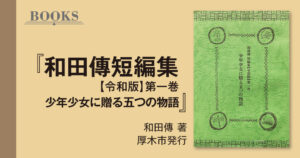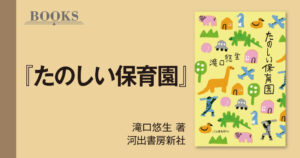詩人が「世界」と言うとき、それは……?
詩人の谷川俊太郎さんが亡くなって、この11月でちょうど1年が経つ。没後半年を経た今年5月、東京都内のホテルで催されたお別れの会には関係者のみ、それでも560人もの人が参列したという。
谷川さんはあまりにも有名な詩人だった。詩だけでなく、エッセイ、童話、絵本をはじめとする翻訳、テレビ・映画のテーマ曲や数百曲に及ぶ各地の学校の校歌の作詞など、92年の生涯にのこした作品は数知れない。それらに一度でもふれ、忘れがたい思いを抱く人々もまた、広い意味での関係者といえるのではないだろうか。
その谷川さんの箴言集ともいうべき本書は、少し変わった性格をもつ。6つのエッセイ集と27の詩のなかから選んだ短い文章と詩句を組み合わせ、「自分」「こころとからだ」「愛」「暮らし」「死」「詩と言葉」など10のテーマに沿ってゆったりと進行してゆく。掲載する言葉を選んで一冊の本に整えたのは、自分ではなく本田道生さんという編集者だったと、氏はあとがきで本書誕生のいきさつを明かしている。
言葉のもつ力と、隅々まで神経の行き届いた本のつくり。新書サイズの小さな本のなかに、深い泉のような世界が広がっている。言葉が読む人の心に届くというより、読む人の心を反対に本のほうが受けとめてくれるような存在。本書を「人生の教科書」と呼ぶ若い読者もいるそうだ。
〈空の青さをみつめていると/私に帰るところがあるような気がする〉〈この地球では/いつもどこかで朝がはじまっている〉〈どんなよろこびのふかいうみにも/ひとつぶのなみだが/とけていないということはない〉といった詩句からは無言の慰謝が感じられ、詩人が〈ほんの些細なことが僕等を人生に気づかせるようになります〉〈もし人間がみにくいとすれば、それは私がみにくいからであり、もし人間がおろかだとすれば、それは私がおろかだということだ〉と語るとき、人はおのずと自らを顧みる。〈遠い国は/おぼろだが/宇宙は鼻の先〉はきわめてシンプルで、虚を突かれるような名言ではあるまいか。
谷川さんが創作においてめざしていたものが、期せずして語られる場面もある。〈純粋というものは、ひとつの郷愁のように、いつも私の心にかかってもいるのである〉〈ぼくらの見栄が言葉を化粧する/言葉の素顔を見たい/そのアルカイック・スマイルを〉といったように。
そして〈愛することで私たちは世界とむすばれている〉〈世界こそ真に美しいただひとつのものなのだ。僕等は常に生命のもっとも深い流れに気づいていなければならない〉、あるいはあとがきの結びの、〈言葉はいつも出発点で、そこから私たちは他者へ、また世界へと向かうのです〉という文章から、私たちは詩人の決意の固さを感じとる。「世界とのむすびつき」は本書のもっとも大切なキーワードで、谷川さんのいう世界とはどんなものなのか、もっと深く知りたくなる。
読者がもう一歩進んで、実際にこれらの詩句や文章を含む作品にふれたとき、もしかすると本書とは異なる印象を抱くことがあるかもしれない。けれどもこれは谷川さんの作品世界への小さな入り口にすぎず、中身をぎりぎりまで削った簡素さゆえに、よりいっそう豊かな言葉の世界を暗示してもいるのだ。
この書はもともと『谷川俊太郎の問う言葉答える言葉』というタイトルで2008年にはじめて世に出、その4年後にはより廉価な新装版が、さらに今年夏、改題・再編集されて刊行された。カバー・表紙の版下に今やぜいたくな活版清刷を用いて美しく仕上げられた、いわば永久保存版である。

谷川俊太郎[たにかわ・しゅんたろう] 1931年、東京生まれ。詩人。1952年、詩集『ニ十億光年の孤独』刊行以来、多くの作品を発表している。また、童話・絵本・翻訳などの分野でも、幅広く活躍。詩集に『六十二のソネット』『旅』『夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった』『はだか』『私』『ベージュ』『虚空へ』『どこからか言葉が』など。2024年逝去。

こちらの本(↑)もおすすめです。
『空の青さをみつめていると 谷川俊太郎詩集』(KADOKAWA公式オンラインショップ)
まつなが・ゆいこ 1967年東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。千代田区・文京区界隈の中小出版社で週刊美術雑誌、語学書、人文書等の編集部勤務を経て、 2013年より論創社編集長。